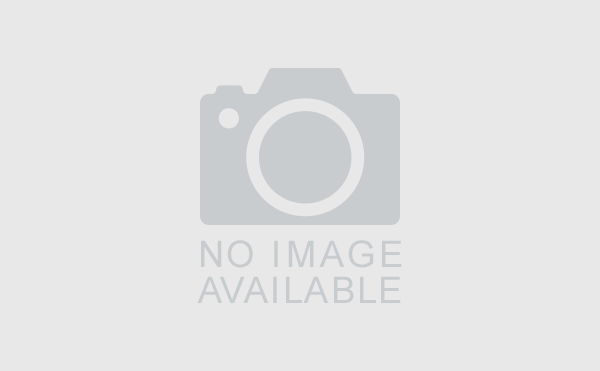誹謗中傷被害を受けたときに使える内容証明の書き方と対応の流れ
Contents
誹謗中傷の被害には内容証明で正式な抗議を|行政書士が解説
東京都江東区のリーリエ行政書士事務所では、契約書作成や内容証明郵便を通じて、法律トラブルの未然防止と解決支援を行っております。
近年は、SNSやブログでの誹謗中傷被害に関するご相談が増加しています。
「どう抗議すればいいのか」「警察に行くしかないのか」と悩む方も少なくありません。
誹謗中傷は精神的なダメージだけでなく、社会的評価や人間関係にも深刻な影響を及ぼします。
感情的な反論では逆効果となる場合もあります。
本記事では、内容証明郵便を活用した誹謗中傷対策の方法・書き方・対応手順を行政書士の立場からわかりやすく解説します。
この記事でわかること
-
誹謗中傷と名誉毀損の違いと法律上の問題点
-
内容証明郵便が有効となる理由と限界
-
具体的な文面テンプレートと書き方の注意点
-
被害を受けたときの対応手順
-
専門家に相談すべきタイミングと注意点
誹謗中傷と名誉毀損:基本的な理解
誹謗中傷とは何か
誹謗中傷とは、SNSや掲示板などで根拠のない悪意ある言動により他人を傷つける行為です。
単なる批判との線引きは難しいですが、相手の名誉や社会的評価を不当に貶める内容であれば、法的に問題となる可能性があります。
名誉毀損との関係
誹謗中傷はしばしば名誉毀損に該当します。
名誉毀損とは、他人の社会的評価を下げるような事実を公に示す行為を指します。
たとえ真実であっても、目的や表現方法によっては違法と判断されることがあります。
名誉毀損が認められると、慰謝料請求・投稿削除・謝罪広告の請求が可能になり、刑事罰(名誉毀損罪)が科される場合もあります。
内容証明郵便が誹謗中傷対策で役立つ理由
内容証明郵便とは
内容証明郵便は、「いつ・誰が・どんな内容を・誰に送ったか」を郵便局が証明してくれる制度です。
通知文の内容・送付日・宛先が第三者機関に記録として残るため、法的証拠力を持ちます。
誹謗中傷対応における利点と限界
内容証明郵便を送ることで、
-
「正式な抗議」を受け取ったという心理的圧力を与えられる
-
今後の法的手続きに備えた証拠の一つになる
という効果があります。
ただし、法的強制力はありません。
削除命令や賠償請求を直接実現するものではなく、あくまで警告・交渉の第一段階として活用します。
内容証明の文面テンプレートと書き方のポイント
【誹謗中傷に対する内容証明郵便の例文】