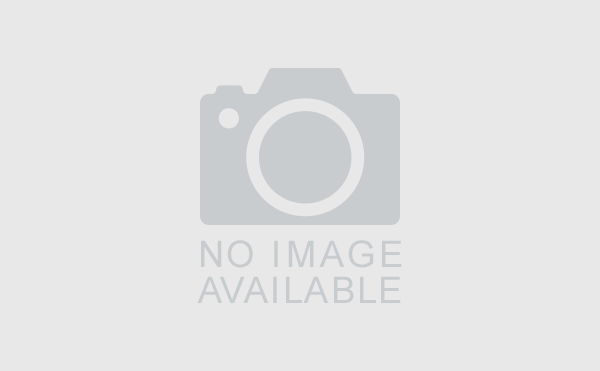準委任契約書のひな形公開!業務委託で失敗しないための項目と注意点を行政書士が解説
「外部に業務を委託したいけれど、どんな契約書を作ればいいの?」「フリーランスとして仕事を受けるけど、契約書の内容はこれで大丈夫?」――特に準委任契約の場合、「成果物」がないため、何に注意して契約書を作成すればいいのか、迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
インターネット上には様々な契約書のひな形がありますが、そのまま利用すると、あなたのビジネスの実態に合わず、後でトラブルになるリスクもあります。適切な契約書は、あなたのビジネスをスムーズに進め、万が一の事態から守るための重要な盾になります。
準委任契約書の作成やチェックに関するご相談が多数寄せられています。この記事では、準委任契約書の基本的な項目と、実務で特に注意すべきポイントを、ひな形(テンプレート)を交えながら行政書士が分かりやすく解説します。このひな形を活用し、あなたのビジネスに最適な契約書を作成し、安心して業務に集中できる環境を整えましょう。
Contents
基礎:準委任契約書の目的と必須項目
準委任契約書は、特定の業務を「すること自体」を委託し、受託者がそれを善良な管理者としての注意義務**を持って遂行することを目的とする契約書です。仕事の完成ではなく、業務の遂行プロセスやサービスの提供に報酬が発生する点が、請負契約書との大きな違いです。
準委任契約書を作成する目的
準委任契約書を作成する主な目的は、以下の通りです。
-
業務内容の明確化: 委託する業務の範囲や内容を具体的に定めることで、双方の認識の齟齬を防ぎます。
-
報酬条件の明確化: 業務の対価として、いくら、いつ、どのように支払うかを明確にし、報酬トラブルを回避します。
-
責任範囲の明確化: どちらの当事者がどのような責任を負うのかを定めることで、万が一のトラブル時に迅速な解決を促します。
-
秘密保持の徹底: 業務を通じて知り得た情報が外部に漏れることを防ぎます。
-
紛争予防: あらかじめトラブルを想定し、解決に向けたルールを定めておくことで、紛争の発生を予防し、発生した場合もスムーズな解決を図ります。
準委任契約書に記載すべき必須項目
準委任契約書には、一般的に以下の項目を記載します。これらの項目が網羅されていることで、法的に有効かつ実務上も使いやすい契約書となります。
-
契約の目的: 何の業務委託に関する契約なのかを明確にします。
-
委託業務の内容: 最も重要です。「何をどこまで行うのか」を具体的に、かつ詳細に記載します。抽象的な表現は避け、具体的な作業内容、提供するサービス、報告の頻度などを盛り込みましょう。
-
例:「月〇回の定例会議への参加」「〇〇に関する市場調査レポートの作成」「顧客からの問い合わせ対応(週〇時間まで)」
-
-
報酬:
-
報酬額: 具体的な金額を明記します。
-
算定方法: 時給、月額固定、業務単位など、報酬の算定方法を明確にします。
-
支払方法: 振込先、支払期日などを定めます。
-
消費税: 消費税込みか税抜きかも明記します。
-
-
契約期間: 契約の開始日と終了日を明確にします。自動更新の有無も記載します。
-
契約解除: どのような場合に契約を解除できるのか、解除時の通知期間などを定めます。
-
善管注意義務: 受託者が善良な管理者としての注意義務を負うことを明記します。
-
秘密保持: 業務上知り得た情報の取り扱いについて定めます。特に重要な情報を取り扱う場合は、別途「秘密保持契約(NDA)」を締結することも検討しましょう。
-
損害賠償: 契約違反があった場合の損害賠償の範囲や上限額について定めます。
-
権利義務の譲渡禁止: 契約上の地位や権利義務を、相手方の承諾なしに第三者に譲渡することを禁止する条項です。
-
反社会的勢力の排除: 契約当事者が反社会的勢力ではないことを確認し、排除するための条項です。
-
準拠法・合意管轄: 契約に関する紛争が発生した場合に、どの国の法律を適用し、どの裁判所で解決するかを定めます。
-
協議事項: 契約に定めのない事項や、解釈に疑義が生じた場合に、誠意をもって協議する旨を記載します。
これらの項目を漏れなく、かつ具体的に記載することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して業務を進めるための基盤が築かれます。
準委任契約書ひな形(簡易版)
以下に、準委任契約書の簡易的なひな形を提示します。これはあくまで一般的なものであり、個別の業務内容や状況に応じて、適切な修正・加筆が必要です。
**準委任契約書** 委託者 〇〇株式会社(以下「甲」という。)と、 受託者 〇〇(氏名/以下「乙」という。)は、 以下のとおり、準委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。 **第1条(目的)** 甲は乙に対し、以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。 **第2条(本件業務の内容)** 本件業務の内容は、以下のとおりとする。 1. 〇〇に関するコンサルティング業務 2. 月〇回の定例ミーティングへの参加 3. 〇〇に関する調査およびレポート作成(月〇回) 4. その他、甲が別途指定する〇〇に関する業務 **第3条(報酬)** 1. 甲は乙に対し、本件業務の対価として、月額金〇〇円(消費税別途)を支払うものとする。 2. 甲は、前項の報酬を、毎月末日締めの翌月〇日までに、乙が指定する銀行口座へ振込送金により支払う。振込手数料は甲の負担とする。 **第4条(契約期間)** 本契約の有効期間は、20〇〇年〇月〇日から20〇〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の〇ヶ月前までに、いずれの当事者からも書面による終了の意思表示がない限り、本契約は同条件でさらに〇年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 **第5条(善管注意義務)** 乙は、本件業務の遂行にあたり、善良な管理者としての注意義務をもって、誠実にこれを行うものとする。 **第6条(秘密保持)** 1. 甲および乙は、本契約の履行に関して知り得た相手方の営業上、技術上その他一切の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なくして、第三者に開示または漏洩してはならない。 2. 前項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。 **第7条(損害賠償)** 甲または乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。ただし、賠償額は、本契約に基づく月額報酬の〇ヶ月分を上限とする。 **第8条(契約解除)** 甲または乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反が是正されない場合、本契約を解除することができる。 **第9条(協議)** 本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲および乙は、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。 **第10条(合意管轄)** 本契約に関する一切の紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 20〇〇年〇月〇日 (甲) 住所: 名称:〇〇株式会社 代表者:〇〇 〇〇 印 (乙) 住所: 氏名:〇〇 〇〇 印
実務で失敗しないための契約書作成・チェックポイント
上記のひな形はあくまでベースです。あなたのビジネスや委託する業務に合わせて、以下の点を特に注意して作成・チェックしましょう。
-
「委託業務の内容」は具体的に、かつ例外を想定する
-
最もトラブルになりやすい項目です。「何となくこんなことをしてくれるだろう」という曖昧さは禁物。
-
具体的な作業内容、成果物の有無(準委任なので「報告書」など)、報告頻度、コミュニケーション方法などを明記しましょう。
-
「想定外の業務」が発生した場合の対応(追加報酬の有無、別契約とするかなど)も、契約書に明記しておくと安心です。
-
-
報酬条件は「作業量」と「期間」を明確に
-
準委任契約では、成果の有無に関わらず、業務を遂行したこと自体に報酬が発生します。
-
「月額〇円」であれば、その月額に含まれる作業範囲(例:〇時間まで、〇回まで)を明記しましょう。
-
追加業務が発生した場合の報酬や、途中で契約が終了した場合の精算方法も具体的に定めておくと、後の金銭トラブルを防げます。
-
-
契約期間と解除条項は慎重に
-
自動更新の有無: 自動更新条項がある場合は、更新を希望しない場合の通知期間を明確にします。
-
中途解除: 業務内容や相手との関係性によっては、いつでも解除できる「いつでも解除権」を認めるか、一定期間の予告を要するかなどを検討しましょう。相手が著しい義務違反をした場合の解除事由も具体的に記載します。
-
-
損害賠償条項はリスクマネジメントの要
-
上限額の設定: 受託者側であれば、賠償額の上限を「契約金額の〇ヶ月分」などと定めることで、過大な賠償リスクから身を守れます。
-
賠償の範囲: 直接損害に限るのか、間接損害(逸失利益など)も含むのかを明確にしましょう。一般的には直接損害に限定することが多いです。
-
免責事項: 自然災害などの不可抗力による責任免除の条項も忘れずに盛り込みましょう。
-
-
秘密保持義務の範囲と罰則
-
どの情報が秘密情報に該当するのか、利用目的、開示禁止期間などを具体的に定めます。
-
違反した場合の罰則(損害賠償、違約金など)についても検討しましょう。
-
-
個人情報保護に関する条項
-
個人情報を取り扱う業務の場合、個人情報保護法に準拠した取り扱い、安全管理措置、漏洩時の対応などを詳細に定める必要があります。
-
-
印紙税について
-
準委任契約書は、原則として印紙税の課税対象ではありません。ただし、契約内容によっては課税文書(例:請負契約の性質も含む場合)となる可能性もあるため、注意が必要です。
-
まとめ:準委任契約書はあなたのビジネスを守る「地図」
準委任契約書は、単なる書面ではありません。それは、業務の範囲、報酬、責任、そして万が一のトラブル時の解決方法を明確にする、あなたのビジネスを守るための**「地図」**のようなものです。
「ひな形をそのまま使ったから大丈夫」と安易に考えるのではなく、ご自身の業務内容や取引の実態に合わせて、一つ一つの項目を丁寧に検討し、必要な修正を加えることが極めて重要です。この手間を惜しまないことが、後々のトラブルを防ぎ、安心・安全なビジネス運営に繋がります。
あなたのビジネスモデルや業務内容を深く理解し、最適な準委任契約書の作成や、既存契約書のリーガルチェックをサポートいたします。漠然とした不安を抱えたまま契約を結ぶのではなく、専門家のサポートを得て、確実な一歩を踏み出しましょう。
契約書の作成や内容に関する疑問、不安があれば、どうぞお一人で悩まずに、私たちにご相談ください。あなたのビジネスを法的な側面から全力でサポートします。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください。