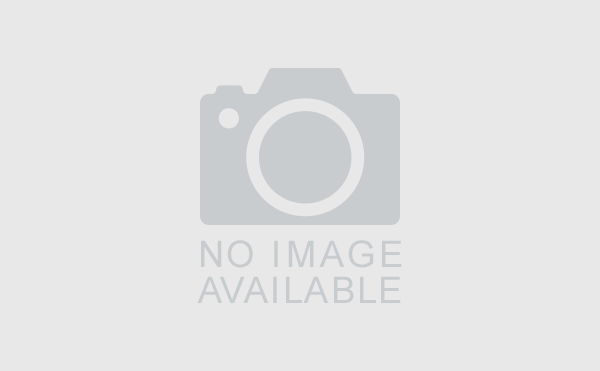住宅宿泊事業法と旅館業法の違いを知らないと違法営業に?行政書士が解説
Contents
はじめに:民泊運営には法制度の正しい理解が不可欠
リーリエ行政書士事務所では、民泊を始めたいという方から「どの法律に基づいて手続きを進めればいいのか分からない」というご相談を多くいただきます。住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊制度など、民泊には複数の法的枠組みがあり、それぞれの要件や手続きが異なるため、正確な理解が求められます。
誤って無許可営業を行ってしまうと、行政からの指導や営業停止命令を受けるリスクがあります。この記事では、民泊に関わる主要な法律である「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「旅館業法」の違いを、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
この記事でわかること
-
住宅宿泊事業法と旅館業法の基本的な違い
-
適用される場面の判断基準
-
各制度の営業日数制限や申請手続きの特徴
-
無許可営業とならないためのポイント
民泊に適用される2つの法制度とは?
住宅宿泊事業法とは
住宅宿泊事業法とは、いわゆる「民泊新法」と呼ばれる制度で、平成30年に施行されました。この法律は、旅館業法の許可を取得せずに、一般住宅を使って宿泊サービスを提供できるようにした新しい枠組みです。
この制度では、年間180日以内であれば、届出を行うことで民泊営業が可能になります。許可ではなく「届出制」である点が特徴であり、比較的手続きのハードルが低く、個人でも始めやすい制度とされています。
旅館業法とは
旅館業法は、従来から存在する「宿泊業」に関する法律で、ホテルや旅館、簡易宿所、下宿などの営業を規制するものです。旅館業法に基づく営業許可を取得すれば、年間の営業日数に制限はなく、自由に宿泊サービスを提供することができます。
一方で、設備基準や管理体制に対する要件が厳しく、消防設備や受付体制などの整備が求められるため、事業として本格的に宿泊施設を運営する方向けの制度です。
両制度の主な違いと適用判断
営業日数の制限
住宅宿泊事業法では、1年間で最大180日までしか営業できません。この上限は全国一律で定められており、超過すると違法営業とみなされます。これに対し、旅館業法では営業日数の制限がないため、通年での営業が可能です。
「できるだけ頻繁に貸したい」「長期で安定的に運営したい」と考える場合は、旅館業法での許可取得を検討すべきです。
許可と届出の違い
旅館業法は「許可制」であり、営業を始める前に都道府県や保健所の審査を受け、基準を満たす必要があります。一方、住宅宿泊事業法は「届出制」であり、要件を満たしたうえで届出を行えば営業が可能になります。
ただし、届出後も、保健所などからの立入検査や報告義務が課されることがありますので、実務上の管理責任は小さくありません。
設備要件と管理体制
旅館業法に基づく施設では、受付・帳場の設置や宿泊者名簿の整備、避難経路の表示、消防設備の設置などが義務付けられます。
住宅宿泊事業法では、こうした設備基準は一部緩和されているものの、代わりに「管理業務の外部委託」や「騒音・ゴミ出しトラブルへの対応体制の整備」など、運営ルールに関する細かな義務が存在します。
実際の相談事例と違法営業のリスク
事例1:住宅宿泊事業法で届出せずに短期貸しを続けて行政指導
東京都内でマンションの一室を短期賃貸として貸し出していたAさんは、「週末だけの貸し出しだから問題ない」と考え、住宅宿泊事業法の届出をせずに運営を続けていました。ところが近隣住民からの通報を受けて保健所の調査が入り、違法営業と認定され、改善命令を受けました。
Aさんは慌てて届出を行い、あらためて消防設備の整備と管理者の配置を進めることになりました。
事例2:旅館業法の許可取得を避けた結果、営業停止処分に
Bさんは、複数の部屋を使って通年営業を行っていましたが、旅館業法の許可を得ていなかったため、条例違反に該当し、営業停止処分を受けました。条例では一定の営業日数を超える宿泊サービスは旅館業法の許可が必要とされており、住宅宿泊事業法では対応できない範囲となっていたのです。
行政書士の指導のもと、改めて旅館業法に基づいた許可申請を行い、営業再開に至りました。
事例3:制度選択を誤りトラブルが発生
Cさんは「手軽に始めたい」という理由で住宅宿泊事業法での届出を選びましたが、長期貸し出しを希望する利用者が多く、結果として180日制限をオーバーする事態に。届出内容と実際の運営が一致していなかったため、行政から改善報告を求められ、運営の見直しを余儀なくされました。
正しい制度選択と行政書士のサポート
自分の運営スタイルに合った制度を選ぶ
「短期的に副業として運営したい」「年間数日しか使わない自宅を有効活用したい」という方には住宅宿泊事業法が適しています。一方、「観光地で本格的に宿泊業を始めたい」「通年営業で収益を上げたい」という方には旅館業法での許可取得が現実的です。
いずれにせよ、自身の物件の所在地や管理規約、地域の条例などを十分に確認したうえで制度を選ぶことが必要です。
行政書士ができること
行政書士は、民泊の届出書類や営業許可申請書の作成、消防計画の確認、管理者選任の助言、近隣住民への説明文書作成など、運営に必要な法的手続きをサポートすることが可能です。
特に、違法営業とならないための事前確認や、行政とのやり取りが苦手な方にとっては、行政書士の関与がリスク回避に大きく貢献します。
まとめ:制度の理解と事前対策で違法リスクを回避
住宅宿泊事業法と旅館業法は、目的や運営スタイルに応じて使い分けるべき別の制度です。知らずに営業を始めてしまうと、違法営業と見なされるリスクがあり、営業停止や罰則の対象にもなり得ます。
民泊を始めたいと考えている方、既に始めているが制度選択に不安がある方は、制度の違いをしっかりと理解し、自分の運営スタイルに合った法的手続きを行うことが重要です。
リーリエ行政書士事務所では、民泊に関する届出、許可申請、運営ルールの整備などを幅広くサポートしています。東京都江東区で民泊を検討している方は、まずは一度ご相談ください。制度の選び方から具体的な手続きまで、丁寧に対応いたします。
はじめに:民泊運営には法制度の正しい理解が不可欠
リーリエ行政書士事務所では、民泊を始めたいという方から「どの法律に基づいて手続きを進めればいいのか分からない」というご相談を多くいただきます。住宅宿泊事業法、旅館業法、特区民泊制度など、民泊には複数の法的枠組みがあり、それぞれの要件や手続きが異なるため、正確な理解が求められます。
誤って無許可営業を行ってしまうと、行政からの指導や営業停止命令を受けるリスクがあります。この記事では、民泊に関わる主要な法律である「住宅宿泊事業法(民泊新法)」と「旅館業法」の違いを、行政書士の視点で分かりやすく解説します。
この記事でわかること
-
住宅宿泊事業法と旅館業法の基本的な違い
-
適用される場面の判断基準
-
各制度の営業日数制限や申請手続きの特徴
-
無許可営業とならないためのポイント
民泊に適用される2つの法制度とは?
住宅宿泊事業法とは
住宅宿泊事業法とは、いわゆる「民泊新法」と呼ばれる制度で、平成30年に施行されました。この法律は、旅館業法の許可を取得せずに、一般住宅を使って宿泊サービスを提供できるようにした新しい枠組みです。
この制度では、年間180日以内であれば、届出を行うことで民泊営業が可能になります。許可ではなく「届出制」である点が特徴であり、比較的手続きのハードルが低く、個人でも始めやすい制度とされています。
旅館業法とは
旅館業法は、従来から存在する「宿泊業」に関する法律で、ホテルや旅館、簡易宿所、下宿などの営業を規制するものです。旅館業法に基づく営業許可を取得すれば、年間の営業日数に制限はなく、自由に宿泊サービスを提供することができます。
一方で、設備基準や管理体制に対する要件が厳しく、消防設備や受付体制などの整備が求められるため、事業として本格的に宿泊施設を運営する方向けの制度です。
両制度の主な違いと適用判断
営業日数の制限
住宅宿泊事業法では、1年間で最大180日までしか営業できません。この上限は全国一律で定められており、超過すると違法営業とみなされます。これに対し、旅館業法では営業日数の制限がないため、通年での営業が可能です。
「できるだけ頻繁に貸したい」「長期で安定的に運営したい」と考える場合は、旅館業法での許可取得を検討すべきです。
許可と届出の違い
旅館業法は「許可制」であり、営業を始める前に都道府県や保健所の審査を受け、基準を満たす必要があります。一方、住宅宿泊事業法は「届出制」であり、要件を満たしたうえで届出を行えば営業が可能になります。
ただし、届出後も、保健所などからの立入検査や報告義務が課されることがありますので、実務上の管理責任は小さくありません。
設備要件と管理体制
旅館業法に基づく施設では、受付・帳場の設置や宿泊者名簿の整備、避難経路の表示、消防設備の設置などが義務付けられます。
住宅宿泊事業法では、こうした設備基準は一部緩和されているものの、代わりに「管理業務の外部委託」や「騒音・ゴミ出しトラブルへの対応体制の整備」など、運営ルールに関する細かな義務が存在します。
実際の相談事例と違法営業のリスク
事例1:住宅宿泊事業法で届出せずに短期貸しを続けて行政指導
東京都内でマンションの一室を短期賃貸として貸し出していたAさんは、「週末だけの貸し出しだから問題ない」と考え、住宅宿泊事業法の届出をせずに運営を続けていました。ところが近隣住民からの通報を受けて保健所の調査が入り、違法営業と認定され、改善命令を受けました。
Aさんは慌てて届出を行い、あらためて消防設備の整備と管理者の配置を進めることになりました。
事例2:旅館業法の許可取得を避けた結果、営業停止処分に
Bさんは、複数の部屋を使って通年営業を行っていましたが、旅館業法の許可を得ていなかったため、条例違反に該当し、営業停止処分を受けました。条例では一定の営業日数を超える宿泊サービスは旅館業法の許可が必要とされており、住宅宿泊事業法では対応できない範囲となっていたのです。
行政書士の指導のもと、改めて旅館業法に基づいた許可申請を行い、営業再開に至りました。
事例3:制度選択を誤りトラブルが発生
Cさんは「手軽に始めたい」という理由で住宅宿泊事業法での届出を選びましたが、長期貸し出しを希望する利用者が多く、結果として180日制限をオーバーする事態に。届出内容と実際の運営が一致していなかったため、行政から改善報告を求められ、運営の見直しを余儀なくされました。
正しい制度選択と行政書士のサポート
自分の運営スタイルに合った制度を選ぶ
「短期的に副業として運営したい」「年間数日しか使わない自宅を有効活用したい」という方には住宅宿泊事業法が適しています。一方、「観光地で本格的に宿泊業を始めたい」「通年営業で収益を上げたい」という方には旅館業法での許可取得が現実的です。
いずれにせよ、自身の物件の所在地や管理規約、地域の条例などを十分に確認したうえで制度を選ぶことが必要です。
行政書士ができること
行政書士は、民泊の届出書類や営業許可申請書の作成、消防計画の確認、管理者選任の助言、近隣住民への説明文書作成など、運営に必要な法的手続きをサポートすることが可能です。
特に、違法営業とならないための事前確認や、行政とのやり取りが苦手な方にとっては、行政書士の関与がリスク回避に大きく貢献します。
まとめ:制度の理解と事前対策で違法リスクを回避
住宅宿泊事業法と旅館業法は、目的や運営スタイルに応じて使い分けるべき別の制度です。知らずに営業を始めてしまうと、違法営業と見なされるリスクがあり、営業停止や罰則の対象にもなり得ます。
民泊を始めたいと考えている方、既に始めているが制度選択に不安がある方は、制度の違いをしっかりと理解し、自分の運営スタイルに合った法的手続きを行うことが重要です。
リーリエ行政書士事務所では、民泊に関する届出、許可申請、運営ルールの整備などを幅広くサポートしています。東京都江東区で民泊を検討している方は、まずは一度ご相談ください。制度の選び方から具体的な手続きまで、丁寧に対応いたします。
詳しくは こちらのサイト をご覧ください。
- カテゴリー
- コラム